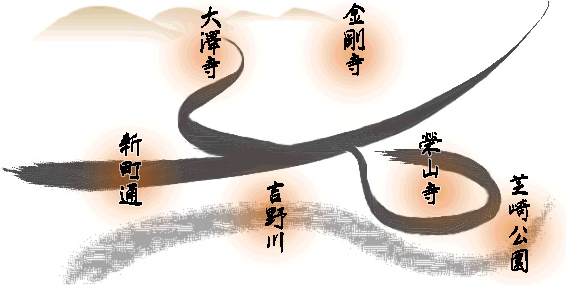
 |
榮山寺 音無川(吉野川)を眼下に望む榮山寺は藤原南家の菩提寺として鎌倉時代になるまで栄華をほしいままにしました。創建は養老3年(719)藤原武智麻呂公によるといわれています。古来は前山寺あるいは崎山寺と呼ばれ、いつしか「榮」の字が当てられたといわれています。「崎」とは岩が川の瀬に張り出したところ、そこには美しいよどみができ、瀬音が消えます。吉野川を「音無川」と呼ぶのはこのためで、川の水色は深みのある瑠璃色、青磁色をしています。この榮山寺には特筆すべきものも多く、法隆寺夢殿とともに奈良時代を代表する国宝「八角堂」や宇治平等院の鐘とともに「平安三絶」の鐘に数えられている梵鐘は、表面の銘文は撰者が菅原道真で筆者が小野道風と伝えられます。 |
▲ | |
 |
新町通 吉野川下流沿いに開けた大和盆地の西南にあたる五條市は、古くから大阪と紀伊を結ぶ交通の要衝でした。そして、東に向かう道を伊勢街道、西へ向かう道を紀州街道と呼んでいました。北をたどれば、荒さか峠を越え、三在から分かれる下街道を通り、奈良盆地へ抜けることができました。また、金剛山地を越えて河内へ抜ける河内街道も通じていました。さらに、吉野川には三十石船や奥吉野から木材を運ぶ筏(いかだ)流しも見られ、水陸交通の要地でもありました。道は、物資の輸送、人の往来だけでなく、文化をも運び、明治の末には鉄道も開通しました。 |
||
| 旧紀州街道には今でも江戸時代の景観を残す街並みが残っており、宿場、商業のまちとして発展した往時の栄華をしのばせています。この街並みの保存を考える自主活動団体「新町塾」は新町通りの活性化と街並みをアピールするため活発な活動をしています。その活動の一環として自由市場「かげろう座」が年に一度開催されています。 | ▲ | ||
 |
吉野川 夏の風物詩のひとつ吉野川の鮎釣り。毎年5月下旬になると鮎釣りが解禁となり、川沿いには思い思いに釣り糸を垂れる太公望でにぎわいます。吉野川・津風呂自然公園の代表的な景勝地、芝崎河川公園では大自然の中でカヌー遊びをする人々に出会います。河川では多くの人々が自然とふれあいながらキャンプやバーベキューを楽しんでいます。また榮山寺周辺の清流や美しい渓谷はハイキングコースとして親しまれています。金剛山の登山道には目に涼やかな高さ約20mの天ケ滝があります。 |
||
| 吉野川祭り 8月15日、16日の2日間、吉野川河川敷では、五條市あげての「吉野川祭り」が開催されます。夕暮れとともに所狭しと夜店が並び、各種イベントで盛り上がります。クライマックスの納涼花火大会では、美しい花火とレーザー光線が夜空を彩ります。祭りのひととき、人々は昼間の暑さを忘れます。 |
 |
▲ | |
 |
大澤寺 “瀬の堂の薬師さん”として土地の人々の厚い信仰を集めているのが大澤寺(だいたくじ)。約1300年前、修験道の開祖役小角(えんのおずぬ)が開基した密教霊場で、境内には諸病平癒(眼病、耳疾、中風、子どものひきつけ)の祈祷所として霊験あらたかな本尊・薬師如来をはじめ、弘法大師お手植えの神樹(智恵の柳)、目を洗うと眼病が治るという通称眼洗い池などがあります。悠久の時を生きているかのような巨樹古木や池の連なる美しい庭園と雅なたたずまいは、訪れる人々の時をしばしとどめてしまうといわれます。瀬の堂」から約2Kmは、格好のハイキングコースとなっています。秋には見事な紅葉で知られています。 |
▲ | |
 |
芝崎公園 大台ヶ原に源に流れる吉野川。その澄んだゆたかな水は、 歳月をこえて尽きることなくとうとうと流れています。その清流と景観美により、昭和47年には榮山寺から上流25キロメートルが「県立吉野川津風呂自然公園」に指定されました。その沿岸にある芝崎公園は、奇岩景勝の場所が多く、史跡めぐりやキャンプ、鮎釣りなど憩いとレジャーのコースとして親しまれています。 |
||
夏場は、鮎釣りやカヌ-の練習場として大勢の人が集まる吉野川河岸。 |
 |
▲ | |
 |
金剛寺 金剛寺は今から800年前平安朝の文化人小松内大臣、平重盛公により創建されました。江戸時代初期から野原城主の畠山義春公の菩提寺として復興、奈良朝の末期、宇智の大野に流されてきた光仁天皇の皇后、井上内親王(いがみないしんのう)とその子の他戸親王(おさべしんのう)の怨霊を祀る宮寺として、また江戸時代の末から明治時代にかけては、奈良唐招提寺の長老の隠居寺、さらには元京都仁和寺、直末の中本寺としての歴史と信仰を有する名刹の古寺でもあり、現在は高野山派に属する真言宗となっています。 |
||
 |
この寺はぼたんの寺として有名で、毎年4月下旬から5月上旬にかけて「ぼたん祭り」が開催されます。境内の吉野川を借景とする約2,000㎡のぼたん園では100種類1,500株のぼたんが今を盛りと咲き誇り、椿、木蓮、平戸、みやこわすれ、石椿花、えびねらん、黄れんげ、樺れんげ、はなみずき、豪華なドイツあやめ等が美しく咲き続けます。このぼたんの起源については文政5年(1822年)当時の本常和尚が薬種として植えたと伝えられています。原産地の中国ではこの根が漢方生薬として栽培されていました。 | ▲ | |